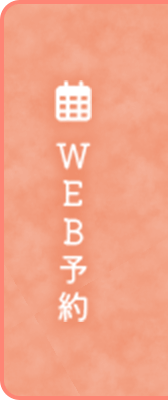こんにちは!姫路市のよつば歯科・小児歯科院長の橋本です!
今回は「子供の口呼吸」についてお話しします。
「寝てる時に口が開いてるけど、大丈夫かな…」
「いつも口がぽかんと開いていて、注意しても治らない…」
そんなお悩みを保護者の方からよくいただきます。
実は、“口で息をする”ということが、お子さんの成長や健康、歯並び、集中力にまで影響を与えているというのをご存知でしょうか?
この記事では、当院が考える「口呼吸の本当の怖さ」と、「どう向き合っていくべきか」をお伝えしたいと思います。
■そもそも口呼吸ってなぜダメなの?
まず前提として、人間の本来の呼吸器官は鼻です。鼻は空気を加湿・加温・濾過(バクテリアやホコリの除去)するフィルター機能を持っていて、これらが免疫機能にも関係しています。
口は“食べる”“話す”ための器官であり、呼吸に最適化された構造ではありません。
つまり、「口呼吸=本来の体の仕組みから逸脱している」状態なのです。
■他院ではあまり語られない“骨格成長”への影響
一般的に、口呼吸によってむし歯や歯周病のリスクが上がるという話はよく聞くかもしれません。
でも、もっと深刻なのは「骨格の発育」に与える影響です。
小児期は、顎の骨や顔面の骨が柔軟で成長の途中段階。
この時期に口呼吸が習慣化してしまうと、
上顎が横に広がらない(鼻呼吸の圧がかからない)
舌の位置が低くなる(口が開くことで、舌が上顎に接しない)
下顎が後退する(開口習慣により筋肉の発達が偏る)
といった問題が出てきます。
結果として、出っ歯・受け口・ガタガタの歯並び・長い顔(面長)など、歯並びだけでなく顔つきそのものに影響を及ぼすこともあるのです。
■姿勢や集中力にまで影響が?
さらに、当院では口呼吸の子の“姿勢”と“集中力”にも注目しています。
口呼吸の子は、酸素をたくさん取り込もうとして無意識に前傾姿勢になります。
するとバランスを取ろうとして猫背になり、姿勢が悪くなります。
姿勢が悪いと、胸郭(肺のあるエリア)が圧迫され、さらに呼吸が浅くなる…という悪循環が起こります。
その結果、酸素供給が不安定になり、集中力の低下や落ち着きのなさ、ひいては学習にも悪影響が出る可能性があると考えています。
実際、「ADHDだと思っていたけど、呼吸と舌のトレーニングで落ち着いた」というケースも報告されており、脳への酸素供給と行動の関係は近年非常に注目されています。
■よつば歯科・小児歯科が行う“根本原因”へのアプローチ
当院では、ただ「口を閉じましょう」「鼻で息をしましょう」と言うだけではありません。
なぜなら、口呼吸の原因は一人ひとり違うからです。
たとえば…
アレルギー性鼻炎による鼻づまり
扁桃腺肥大やアデノイド肥大
舌小帯(ぜつしょうたい)が短く、舌が上にあがらない
頬や唇の筋肉の発達不足
食べるときの咀嚼力が弱い
このように、原因は「鼻」だけではなく「口腔機能」や「筋肉のバランス」にまで及びます。
よつば歯科・小児歯科では、以下のような視点から総合的にアプローチします:
お口周りの筋機能検査
舌の可動域チェック
姿勢・呼吸の観察
鼻腔の通気テスト
MFT(口腔筋機能療法)やあいうべ体操の指導
必要に応じて耳鼻科との連携
一つの方法で解決しようとするのではなく、「お子さまに合った方法を探す」ことを大切にしています。
■口呼吸を放っておくとどうなる?
口呼吸を放置してしまうと、将来的に以下のような問題が起こる可能性があります:
歯並びの悪化
鼻づまりの慢性化
いびきや睡眠時無呼吸
集中力の低下や学習面の遅れ
慢性疲労
顔貌の変化(アデノイド顔貌)
特に「睡眠時の口呼吸症候群」は深刻で、脳の発達や体の回復に影響を与えるため、早期の対策が必要です。
■保護者の方にお願いしたいこと
口呼吸の改善は、一朝一夕にはいきません。
癖を直すのには時間がかかりますし、お子さん自身の意識改革も必要です。
でも、お家でできることもたくさんあります!
食事の時にしっかり噛むこと(左右両方で)
姿勢を整える習慣づけ(椅子の座り方や机の高さ)
寝る前に「鼻で息できるかな?」と声をかける
一緒にあいうべ体操をする
テレビやゲームの時に「お口、閉じようね」と優しく声がけ
など、毎日の小さな積み重ねが、お子さんの未来を変えます。
■最後に:呼吸は“健康の入り口”
口呼吸は、決して“ちょっとしたクセ”ではありません。
それは、お子さまの心と体の成長にブレーキをかけるサインかもしれません。
よつば歯科・小児歯科では、お口だけを見るのではなく、「全身の健康」と「将来の成長」を見据えて診療を行っています。
「うちの子、口が開いてるな」と少しでも気になったら、ぜひ一度ご相談ください。
一緒にお子さんの呼吸と成長を見守っていけたら嬉しいです!