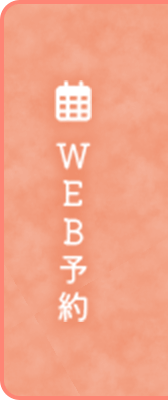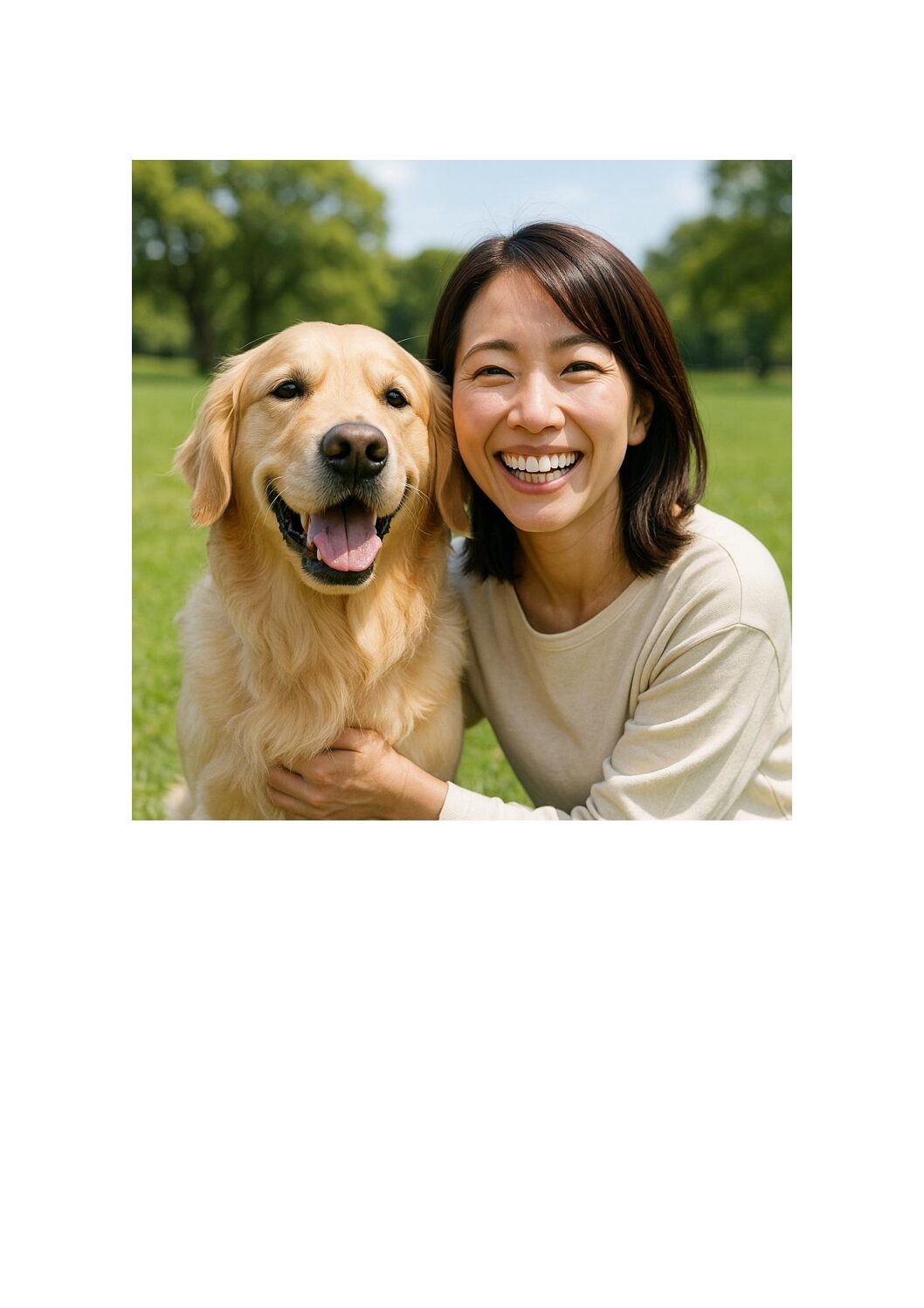
姫路市のよつば歯科・小児歯科 院長の橋本です。 私たちのクリニックには、お子様から大人の方まで、幅広い年齢層の患者様にご来院いただいております。そして、最近では、お口の健康について、ご自身のことはもちろん、大切なご家族、特に「愛犬」の歯の健康についてもご相談いただく機会が増えてきました。
「うちの犬、口が臭くて…」「歯ぐきが赤くなっているみたいで心配」
そういったお声を聞くたびに、歯科医師として、人と犬の絆の深さを改めて感じています。 しかし、その深い絆の中には、もしかしたら「歯周病」という、目に見えない脅威が潜んでいるかもしれない、ということをご存知でしょうか?
「え?歯周病が犬にうつるの?」「まさか、犬から私にうつるなんてことあるの?」
そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。 実は近年、歯周病が人と動物の間で感染し合う「人獣共通感染症(ズーノーシス)」である可能性が指摘され、多くの研究が進められています。 今回は、この「歯周病の人獣共通感染症」というテーマについて、最新の論文に基づいた情報と、私たちよつば歯科・小児歯科が考える歯周病ケアの重要性について、詳しくお伝えしていきたいと思います。
歯周病とは?~人にも犬にも共通する「沈黙の病」~
まず、歯周病とはどのような病気なのかを簡単にご説明しましょう。 歯周病は、歯と歯ぐきの境目に溜まるプラーク(歯垢)の中にいる細菌によって引き起こされる感染症です。これらの細菌が歯ぐきに炎症を起こし、進行すると歯を支える骨(歯槽骨)を破壊し、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともある、非常に恐ろしい病気です。 自覚症状が出にくいことから「沈黙の病」とも呼ばれ、気づいた時にはかなり進行しているケースも少なくありません。
この歯周病は、人間だけでなく、犬にとっても非常に身近な病気です。 犬の歯周病は、3歳以上の犬の80%以上が罹患していると言われるほど、多くの犬が抱える問題です。人間と同様、歯周病菌によって歯ぐきの炎症から始まり、放置すると歯の喪失だけでなく、心臓病や腎臓病など全身の健康にも悪影響を及ぼすことがわかっています。
人と犬、見た目は違えど、歯周病という病気のメカニズムや、それがもたらす影響には、多くの共通点があるのです。
驚愕の事実!歯周病は犬から人に、人から犬に感染する?
さて、本題に入りましょう。歯周病が人と犬の間で感染し合う、という話に疑問を感じる方もいるかもしれません。しかし、近年の研究により、その可能性を示すデータが多数報告されています。
- 人の歯周病菌が犬の口から検出されるケース
これまでの研究で、人の歯周病の主要な原因菌として知られる特定の細菌が、歯周病に罹患している犬の口腔内から検出される事例が報告されています。
例えば、Porphyromonas gingivalis(ポルフィロモナス・ジンジバリス)は、ヒトの慢性歯周炎の主要な病原菌として広く認識されています。この細菌は、非常に毒性が強く、歯周組織の破壊に深く関与していることが知られています。 興味深いことに、このP. gingivalisが、歯周病を患う犬の口腔内からも検出されたという報告が複数あります。
また、Aggregatibacter actinomycetemcomitans(アグリゲイトバクター・アクチノミセテムコミタンス)も、ヒトの侵襲性歯周炎(現在では「壊死性歯周病」に分類されることも多い)の主要な原因菌とされています。この菌もまた、犬の歯周病病変から検出されたという報告があります。
これらの研究結果は、飼い主と愛犬の間で、口腔内の細菌が直接的に伝播している可能性を示唆しており、密接な接触がある場合に、そのリスクが高まると考えられます。
- 犬の歯周病菌が人の口から検出されるケース
さらに興味深いことに、その逆、つまり「犬の歯周病菌が人の口から検出される」という報告も増えています。
犬の歯周病に特有の菌として知られるPorphyromonas gulae(ポルフィロモナス・グラエ)は、犬の歯周病の主要な病原菌の一つです。 このP. gulaeが、犬と密接に生活している人の口腔内から検出されたという事例が報告されています。
これらの研究は、人から犬へ、そして犬から人へ、双方向に歯周病菌が伝播する可能性、つまり「人獣共通感染症」としての側面を強く示唆しています。 特に、飼い主が歯周病を患っている場合、その口腔内の細菌が愛犬に伝播し、愛犬の歯周病を悪化させる可能性が考えられます。逆に、愛犬が歯周病を患っている場合、その細菌が飼い主の口腔内に入り込み、人の歯周病発症や悪化のリスクを高める可能性も否定できません。
- 感染経路は?
では、どのようにしてこれらの菌は伝播するのでしょうか? 考えられる主な感染経路は以下の通りです。
- 舐める行為: 犬が飼い主の口元や顔を舐める行為は、非常に頻繁に行われます。この際、唾液を介して細菌が伝播する可能性が最も高いと考えられます。
- 食器の共有: 同じ食器を共有したり、犬が飼い主の食べ残しを食べたりすることも、菌の伝播経路となり得ます。
- 口腔ケア用品の共有: 稀なケースかもしれませんが、歯ブラシやデンタルフロスなどの口腔ケア用品を共有することは絶対に避けるべきです。
- 接触機会の多さ: 日常的な抱擁や添い寝など、愛犬との密接な接触が多いほど、菌の伝播リスクは高まると考えられます。
これらの感染経路は、私たちと犬との間の「絆」の象徴とも言える行為の中に潜んでいます。だからこそ、正しい知識を持ち、適切な対策を講じることが重要になります。
人獣共通感染症としての歯周病が持つ意味
歯周病が人獣共通感染症である可能性があるということは、単に「細菌がうつる」という話に留まりません。そこには、私たちの大切な家族の健康を守る上で、非常に重要な意味が隠されています。
- 相互感染による歯周病の悪化リスク
もし歯周病菌が人から犬へ、犬から人へ伝播し合うのであれば、以下のような悪循環が起こる可能性があります。
- 飼い主の歯周病が犬の歯周病を悪化させる: 飼い主の口腔内にいる強力な歯周病菌が犬に伝播し、愛犬の歯周病の発症や進行を加速させる可能性があります。
- 犬の歯周病が飼い主の歯周病を悪化させる: 逆に、犬の口腔内にいる歯周病菌が飼い主の口腔内に入り込み、飼い主の歯周病のリスクを高めたり、既存の歯周病を悪化させたりする可能性があります。
これは、どちらか一方だけが口腔ケアをしても、もう一方から再感染してしまい、なかなか歯周病が改善しない、という状況を引き起こしかねないことを意味します。
- 全身疾患への影響リスク
歯周病は、単に口の中だけの病気ではありません。全身の健康に様々な悪影響を及ぼすことがわかっています。
- 人における全身疾患との関連: 歯周病は、糖尿病、心臓病、脳卒中、誤嚥性肺炎、さらには早産・低出生体重児出産などのリスクを高めることが多くの研究で報告されています。口腔内の炎症が全身に波及することで、これらの病態を悪化させると考えられています。
- 犬における全身疾患との関連: 犬においても、歯周病は心臓病(特に弁膜症)、腎臓病、肝臓病などの全身疾患と関連があることが指摘されています。口腔内の細菌や炎症性物質が血流に乗って全身に広がり、臓器に負担をかけると考えられています。
もし、人から犬へ、犬から人へ歯周病菌が伝播し、両者の歯周病が悪化するとすれば、それはそれぞれが抱える全身疾患のリスクをも高めることになります。大切な家族である犬と飼い主が、お互いの健康を脅かし合うという、悲しい事態に繋がりかねないのです。
- 予防と早期治療の重要性がさらに高まる
歯周病が人獣共通感染症である可能性が示唆されたことで、これまで以上に歯周病の「予防」と「早期治療」の重要性が浮き彫りになります。
- 人: 飼い主自身が口腔内の健康を保つことは、犬への歯周病菌の伝播を防ぐだけでなく、犬からの菌の伝播リスクを低減することにも繋がります。
- 犬: 犬の口腔ケアを徹底し、歯周病を予防・治療することは、犬自身の健康を守るだけでなく、飼い主への菌の伝播リスクを低減することにも繋がります。
このように、人と犬の歯周病は、独立した問題ではなく、相互に関連し合う「家族の健康問題」として捉えるべき時期に来ているのです。
では、どうすればいいの?~大切な家族を守るための歯周病ケア~
歯周病が人獣共通感染症である可能性を知った上で、私たちはどのように行動すべきでしょうか。悲観的になる必要はありません。適切な知識と行動で、大切な家族の健康を守ることができます。
- 人の口腔ケアの徹底
まずは、飼い主であるご自身の口腔ケアを徹底することが何よりも重要です。
- 毎日の丁寧な歯磨き: 歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを併用し、歯と歯の間、歯ぐきの境目のプラークを徹底的に除去しましょう。
- 定期的な歯科検診とプロフェッショナルケア: ご自宅でのケアだけでは取り除けない歯石や、歯周ポケットの奥に潜む細菌は、歯科医院での専門的なクリーニング(PMTC)で除去する必要があります。定期的に歯科検診を受け、歯周病のチェックとクリーニングを行いましょう。
- 歯周病の早期発見・早期治療: 歯ぐきの腫れや出血、口臭など、気になる症状があれば、放置せずにすぐに歯科医院を受診しましょう。早期発見・早期治療が、歯周病の進行を食い止める鍵となります。
- 生活習慣の見直し: 喫煙は歯周病を悪化させる最大の要因の一つです。また、ストレスや不規則な生活、偏った食生活も免疫力を低下させ、歯周病のリスクを高めます。健康的な生活習慣を心がけましょう。
- 犬の口腔ケアの徹底
飼い主様ご自身のケアと並行して、愛犬の口腔ケアも徹底しましょう。
- 毎日の歯磨き: 犬用の歯ブラシや歯磨きシート、歯磨きペーストを使って、毎日歯磨きを行うのが理想です。子犬の頃から慣れさせることで、スムーズに歯磨きができるようになります。
- 定期的な動物病院でのデンタルケア: ご自宅での歯磨きだけでは取り除けない歯石や、進行した歯周病は、動物病院での専門的な処置(全身麻酔下での歯石除去や抜歯など)が必要になります。定期的に動物病院で口腔内のチェックを受け、必要に応じて処置を受けましょう。
- デンタルおやつやデンタルフードの活用: 歯磨きを嫌がる犬には、歯石の付着を抑制する効果が期待できるデンタルおやつやデンタルフードを活用するのも一つの方法です。ただし、これらはあくまで補助的なものであり、歯磨きの代わりにはなりません。
- 口臭や歯ぐきの異常に注意: 愛犬の口臭が強くなったり、歯ぐきが赤く腫れていたり、出血が見られたりする場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。
- 人と犬の接触時の注意点
過度に神経質になる必要はありませんが、細菌伝播のリスクを低減するために、いくつかの点に注意しましょう。
- 口元の舐める行為の制限: 特に、犬の口臭が強い場合や、飼い主ご自身が歯周病を患っている場合は、お互いの口元に直接触れる舐める行為は控えめにしましょう。
- 食器の共有を避ける: 人と犬で食器を共有することは避け、それぞれ専用の食器を使用し、清潔に保ちましょう。
- 手洗いの徹底: 犬と触れ合った後や、犬の口腔ケアを行った後は、しっかりと手洗いをしましょう。
よつば歯科・小児歯科が考える「家族みんなの歯周病ケア」
私たちよつば歯科・小児歯科は、歯周病が「人獣共通感染症」としての側面を持つ可能性に着目し、地域の皆様の健康をサポートしていきたいと考えています。 もしかしたら、愛犬の口臭が、ご自身の歯周病のサインである可能性も、その逆も十分にありえます。
歯周病は、放置すれば歯を失うだけでなく、全身の健康にまで悪影響を及ぼす病気です。そして、その影響は、大切な家族である愛犬にも及ぶ可能性があるのです。
「歯周病ケアは、自分だけのものではない。特に愛犬との健やかな生活を守るための大切なケアである。」
私たちは、この視点に立ち、患者様お一人おひとりの口腔内の状態を丁寧に診察し、それぞれに最適な治療計画をご提案いたします。そして、歯周病の治療だけでなく、歯周病にならないための予防ケアにも力を入れています。
「歯周病は遺伝するから仕方ない…」「もう歳だから歯周病は治らない…」 そう諦めてしまっている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、歯周病は、適切なケアと治療によって、その進行を食い止め、改善させることが十分に可能です。
当院では、最新の設備と、豊富な知識・経験を持つ歯科医師、歯科衛生士が、患者様のお口の健康を全力でサポートいたします。
- 精密な検査と診断: 歯周病の進行度合いを正確に把握するための詳細な検査を行います。
- 丁寧な歯周病治療: 歯周ポケットの清掃、歯石除去、歯根面デブリードマンなど、患者様一人ひとりに合わせた治療を行います。
- 徹底した予防ケア: 定期的なプロフェッショナルクリーニング(PMTC)や、歯磨き指導を通じて、歯周病の再発を防ぎます。
- 食生活や生活習慣のアドバイス: 歯周病と深く関わる生活習慣についても、専門的なアドバイスを行います。
そして何より、患者様ご自身が「自分の歯を守りたい」「大切な家族と一緒に健康でいたい」という気持ちを持てるよう、分かりやすい説明と温かいサポートを心がけています。
おわりに:今日から始める、家族の歯周病ケア
愛犬の口の臭いが気になる、歯ぐきが腫れているように見える… ご自身の歯ぐきから血が出る、口臭が気になる、歯がグラグラする…
もし、一つでも当てはまる症状があれば、それは歯周病のサインかもしれません。 そして、そのサインは、あなたと愛犬、お互いの健康に関わる重要なメッセージである可能性があります。
大切な家族である愛犬との絆を深めるために、そして、長く健康な毎日を共に過ごすために、今日から歯周病ケアを始めませんか?
よつば歯科・小児歯科では、患者様の口腔内の健康だけでなく、その先にある豊かな生活まで見据えたサポートを行っています。 ご自身の歯周病ケアを通じて、愛犬の健康も守る。 私たちと一緒に、家族みんなで健康な笑顔を育んでいきましょう。
まずは、お気軽によつば歯科・小児歯科にご相談ください。 皆様のご来院を心よりお待ちしております。
よつば歯科・小児歯科
679-2124 兵庫県姫路市豊富町甲丘3丁目88
電話番号:079-264-1758
HP: https://toyotomi-yotsuba-dc.com/
【Reference】
- Arimoto, S., Konno, H., Sekino, T., Kaneko, N., Kaji, T., & Konishi, T. (2018). Detection of Porphyromonas gingivalis in canine periodontitis. Journal of Veterinary Medical Science, 80(7), 1184-1188.
- Inui, K., Miyasaka, T., Tanaka, A., Yonezawa, K., Kawamura, K., & Takata, T. (2013). Detection of Aggregatibacter actinomycetemcomitans in periodontitis-affected dogs. Journal of Veterinary Medical Science, 75(11), 1475-1478.
- Arimitsu, N., Kato, M., Hamada, M., Sugawara, N., Kawakami, K., & Kawakami, H. (2019). Detection of Porphyromonas gulae in human oral cavity. Journal of Periodontal Research, 54(6), 570-575.